親和を持つカードには、以下のような記述があります。
親和(〜)
〜の部分には、カードの種類がはいります。そして、自分がコントロールする〜の枚数分、プレイするためのコストが(1)軽減されます。
たとえば、《金属ガエル》は以下のような記述になっています。
金属ガエル
Frogmite
(4)
アーティファクト・クリーチャー
[2/2]
親和(アーティファクト) (この呪文をプレイするためのコストは、あなたがコントロールするアーティファクト1つにつき(1)少なくなる。)
《金属ガエル》は4マナ2/2クリーチャーですが、親和(アーティファクト)を持っているので、あなたがアーティファクトを1枚コントロールしていれば、3マナでプレイすることができます。2枚あれば2マナ、4枚あればなんとタダで場に出せるのです。
最も簡単な親和活用法は、アーティファクトデッキを作ることでしょう。ミラディンにはアーティファクトでもある土地もありますから、デッキのカードをすべてアーティファクトにすることさえ可能です。そうすれば、親和(アーティファクト)を持つカードを驚くほど安価にプレイすることができます。2〜3ターン目に《金属ガエル》や《マイアの処罰者》を0マナでプレイし、青マナ1枚で《物読み》をプレイして手札を補充、そして止めは超巨大な《ブルードスター》。こんなデッキが簡単に組めてしまいますね。
でも、デッキのカードがほとんどアーティファクトだと、アーティファクト除去や全体除去に極端に弱くなってしまいます。たとえば《アクローマの復讐》1発で、あなたのコントロールするカードはすべて吹き飛んでしまいますので、ほどほどにしておいたほうがいいかもしれません。
親和デッキについて
実際に、現在のトーナメントシーンでは、親和デッキと呼ばれるデッキが猛威を振るっており、現環境最強のデッキとも言われています。これは、親和そのものの能力の強さおよび驚異的な展開能力にもありますが、それに付随した強力カード、《大霊堂の信奉者》やダークスティールで登場した電結能力を持つクリーチャー(特に《電結の荒廃者》)、非常に軽コストで何度でも手札を補充できる《頭蓋骨絞め》などの力によるところも大きいですね。
残念ながら親和で軽減できるコストは(1)のように○に囲まれた数字で示されているもの(不特定マナ)だけです。たとえば、《物読み》のマナ・コストは(4)(青)ですが、あなたが5つアーティファクトをコントロールしているとしても、《物読み》をプレイするいためには、(青)を払わなければなりません。
ミラディンの親和カードは、たしかにすべて「親和(アーティファクト)」となっています。しかし、親和がアーティファクトに限定した能力であるなら、わざわざ「(アーティファクト)」という表記をつける必要はないわけで、これはアーティファクト以外の親和能力を出すことを前提としたデザインであることを暗に示しています。今後、アーティファクト以外の親和能力が登場することも十分考えられます。
ダークスティールで、アーティファクトでない親和能力が登場しました。「親和(森)」「親和(山)」「親和(沼)」「親和(平地)」「親和(島)」という5種類で、それぞれカッコ内に示された基本地形タイプを持つ土地をコントロールしている枚数によって、プレイするためのコストが軽減されます。
あなたは、《彩色の宝球》を1枚コントロールしていますが、土地は4枚しかなく4マナしか払うことはできません。また、青マナを出す土地はありません。この状態で、《物読み》をプレイできるでしょうか?
《物読み》のマナ・コストは(4)(青)ですが、親和(アーティファクト)があるので、《彩色の宝球》をコントロールしていれば、(3)(青)でプレイできます。しかし青マナが出せません。《彩色の宝球》の能力をプレイすれば青マナを出すことができますが、そうするとコントロールしているアーティファクトがなくなるので、《物読み》のプレイに必要なコストは(4)(青)になってしまい、今度はマナが足りません。なので、プレイすることは不可能、、、のように見えるのですが実はプレイ可能なのです。
これには少し複雑なテクニックが必要です。呪文をプレイするとき、多くの方はまずマナを出してから呪文をプレイしていると思いますが、実際にはその必要はありません。先に呪文をプレイし、支払うべきコストが決定した後でマナを出してコストを支払うことが可能なのです。マナ能力は通常の起動型能力と異なり、呪文をプレイしている最中にもプレイできるのです。これを利用し、まず《物読み》のプレイを宣言し、そしてプレイに必要なコスト(その時点ではアーティファクトが1枚あるので(3)(青)でOK)を決定し、それから《彩色の宝球》のマナ能力をプレイして青マナを出し、そのマナをコストの支払いに充てればいいのです。
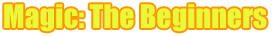
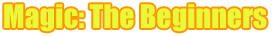
 親和はプレイするコストを軽減する能力だ!
親和はプレイするコストを軽減する能力だ!
 アーティファクト満載の、アーティファクトデッキを作ろう!
アーティファクト満載の、アーティファクトデッキを作ろう!
 親和で色マナは軽減できない!
親和で色マナは軽減できない!
 親和はアーティファクトだけではない!
親和はアーティファクトだけではない!
 マナ・コストは変わらない!
マナ・コストは変わらない!
 微妙にプレイ可能!
微妙にプレイ可能!
