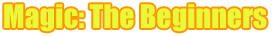 |
解説 〜 フラッシュバック |
フラッシュバックとは?
フラッシュバックを持つカードはカードテキストに「フラッシュバック:(コスト)」と表記されています。
フラッシュバックを持つカードが墓地にある場合、そのフラッシュバックコストを支払うことにより、そのカードを墓地からプレイすることができます。そして、そのカードはゲームから取り除かれます。つまり、フラッシュバックとは墓地にあるカードをもう一度使うことのできる能力なのです。

墓地にあるカードが使える!
フラッシュバックの利点
単純に、フラッシュバックを持つカードは、1枚で2回プレイすることができます。もちろんこれだけで非常に強力です。普通、マジックのカードは1回しかプレイすることはできません。一度プレイした呪文(インスタント、ソーサリー)は墓地に置かれ、もう使うことはできません。もう一度使うには、運に頼って同じカードをもう一度引くしかありません。
しかし、フラッシュバックを持つカードは1枚引くと確実に2回使えるのです。一度使ってもそれは墓地に置かれ、墓地にある間はいつでもつかえるのです。これは、手札が1枚増えたに等しいことです。それどころか、フラッシュバックを持つカードは2枚、3枚と墓地にあれば、手札が2枚、3枚増えたに等しいのです。マジックにおいて、手札の枚数の重要性は言うまでもないでしょう。手札が多いプレイヤーほど、ゲームを有利に進めることができるのです。

フラッシュバックは1枚で2度美味しい。!
フラッシュバックコストに関する考察
フラッシュバックをプレイするには、フラッシュバックコストを支払う必要があります。一般的には、フラッシュバックコストは、マナ・コストよりも大きく設定されているものが多いのですが、中にはその逆もあります。また、フラッシュバックコストとマナ・コストにそんなに差がないものもあります。通常は、マナ・コストが低い呪文は、フラッシュバックコストはかなり大きくなっており、フラッシュバックコストが安いものは、マナ・コストが安くなっています。
これにより、簡単には2度使うことができないようになっています。たとえば、《炎の稲妻》はマナ・コストが(赤)の、2点のダメージを与えるソーサリーですがそのフラッシュバックコストは、(4)(赤)です。手札にある《炎の稲妻》は、1ターン目から使うことができますが、これをフラッシュバックでプレイするにはかなり後になるまで待たなくてはなりません。逆に《ワームの咆哮》は(6)(緑)で6/6トークンを生み出すソーサリーですが、フラッシュバックコストは(3)(緑)です。墓地にあれば早いターンにプレイできますが、普通は7マナ出せるようになるまで待たなくてはなりません。
このように、そう簡単には2度使えないようになっているものが多いのですが、中には簡単に使えるものもあります。《獣群の呼び声》は(2)(緑)の3/3トークンを生み出すソーサリーですが、フラッシュバックコストは(3)(緑)。まず3ターン目にプレイし、すぐ4ターン目にフラッシュバックでプレイすることができます。こういったものは、フラッシュバックを持つ呪文の中でも使い勝手がよく、強力だといえるでしょう。また、中にはフラッシュバックコストにマナが必要ないものもあります。《かな切るときの声》のフラッシュバックコストは、白いクリーチャーを3体タップすることです。この呪文の効果は、白の鳥クリーチャー・トークン2個を場に出すことですので、それ以外に1体白いクリーチャーがいれば、自分自身で生み出したトークンをフラッシュバックコストの支払いに使うことができます。つまり、ほぼ確実に1ターンでフラッシュバック含めて2回プレイすることができるわけで、これは非常に強力です。

フラッシュバックコストに注意しよう!
フラッシュバックの欠点
このように、いいことづくめのように見えるフラッシュバックですが、欠点はないのでしょうか?あえて言うなら、同じ効果を持つフラッシュバックを持たない呪文よりもマナ・コストがやや重く設定されていることが多い、墓地のカードは相手にも見えているので、こちらの魂胆がある程度相手にわかってしまう。同じオデッセイの新ルールであるスレッショルドと相性が悪いなどがあります。

フラッシュバックにも欠点はある!
フラッシュバックの効果的な使い方
《獣群の呼び声》などのコストの軽いフラッシュバック呪文は普通に使っても強力なのですが、《ワームの咆哮》のように使いにくいものもあります。しかしながら、《ワームの咆哮》はフラッシュバックでプレイすれば、たったの4マナで6/6のクリーチャーを生み出す、非常に強力なカードです。しかしながらマナ・コストは(6)(緑)なので、これを普通に使うなら、まずは7枚土地が出るまで待ち、まず一度プレイして墓地に落とし、そして次のターンにもう一度プレイすることになります。これで、6/6トークンを2個出すことができるわけですが、7マナ出せるようになるのはほとんどゲームも終了まぎわであることが多く、それ以前にゲームが終わってしまうことだって多いでしょう。これでは使い物にはなりません。
しかし、墓地にあれば4マナでプレイできるのに、7マナ溜まるまで待たなければならないのはあまりにももったいないですね。ですので、手札からプレイすることは考えず、最初からフラッシュバックでプレイすることを考えましょう。何らかの方法で、《ワームの咆哮》を直接墓地に落とせば、4ターン目、あるいは3ターン目に6/6クリーチャーを出すなどという傍若無人なことができてしまいます。これは非常に強力です。墓地に落とすには、《野生の雑種犬》などの共鳴者や、《マーフォークの物あさり》のようなドロー&ディスカード効果で手札から捨てる、あるいは《物静かな思索》で直接墓地から探してきて墓地に置くなどの方法があります。特に《物静かな思索》を使う方法は確実性が高く、一度に3枚墓地に置くことができるため、非常に強力です。これはようするにライブラリから好きなカードを3枚ドローしているのに等しいのです。
《ワームの咆哮》以外にも、同じような使い方のできるフラッシュバックカードはいろいろあります。活用してみましょう。

マナ・コストが高くても、直接墓地に落とせばOK!
フラッシュバックへの対処法
今度は、相手がフラッシュバックを使っているときの対処法について考えてみましょう。もっとも、対策といっても相手の墓地のカードを取り除くくらいしか手はありません。しかし、そのタイミングには注意する必要があります。そのフラッシュバックカードがインスタントである場合、それをゲームから取り除こうとしても、対応してプレイされてしまうことが考えられます。ですので、その場合は相手の使えるマナがないときを狙ってプレイする必要があります。また、ソーサリーであっても相手のターンであれば、相手に優先権があるため、ゲームから取り除こうとしても先にプレイされてしまいます。自分のターン、あるいはメインフェイズ以外で行うほうがいいでしょう。また、相手がフラッシュバックをプレイしたとき、それに対応してそのカードをゲームから取り除くことはできません。なぜなら、プレイしたカードはスタックに移動してしまうため、もう墓地には存在しないからです。
また、《ワームの咆哮》のようなマナ・コストの重いフラッシュバックカードであれば、ジャッジメントの代言者で相手の手札に戻してしまうという手もありますが、《野生の雑種犬》あたりがいると逆効果になりますし、あまり現実的とはいえないでしょう。
最も確実なのは《消えないこだま》でしょうか。これは相手の墓地にカードを一掃した上、同じカードをライブラリからも取り除いてくれます。うまく決まればこれ一発でゲームに勝つこともできるでしょう。

墓地から取り除け!
フラッシュバック裁定集
- フラッシュバックを持つカードが墓地にある場合でも、それは通常と同じタイミングでしかプレイできない。それがソーサリーであれば、それを墓地からプレイできるのは、やはり自分のターンのメインフェイズでスタックが空のときだけである。
- フラッシュバックでプレイされた呪文は、通常にプレイされた呪文と何ら変わりない。《対抗呪文》などで打ち消すこともできるし、「〜をプレイしたとき」などに誘発する誘発型能力も通常通り誘発する。
- フラッシュバックでキッカーを持つ呪文をプレイした場合、そのキッカーコストを支払うことができる。他の追加コストについても同様である。
- フラッシュバックでプレイされた呪文を、《記憶の欠落》で打ち消した場合、そのカードはライブラリのトップには置かれず、ゲームから取り除かれる。フラッシュバックは、呪文が解決した後その呪文が「どこか」へ移動することを「ゲームから取り除く」ことに置き換えるからである。
- フラッシュバックでバイバックを持つ呪文をバイバックコストを支払ってプレイした場合、そのカードは手札には戻らずゲームから取り除かれる。フラッシュバックは、呪文が解決した後その呪文が「どこか」へ移動することを「ゲームから取り除く」ことに置き換えるからである。
- フラッシュバックでプレイした呪文を、《呪文乗っ取り》で打ち消され、それがゲーム外からプレイされた場合、そのカードは通常通りオーナーの墓地に置かれる。その呪文はフラシュバックでプレイしたのではないからである。
- フラッシュバックを持つ呪文に、《埋め合わせ》をプレイした場合、そのカードは2つのフラッシュバックコストを持つことになる。そのどちらを支払うことによっても、そのカードをフラッシュバックでプレイすることができる。
- マナ・コストに(X)を含む呪文に《埋め合わせ》をプレイした場合、そのカードはフラッシュバックコストにも(X)を含むことになる。(X)はプレイするときにそのプレイヤーが決めることができる。
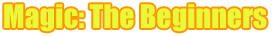
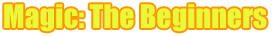
 墓地にあるカードが使える!
墓地にあるカードが使える!
 フラッシュバックは1枚で2度美味しい。!
フラッシュバックは1枚で2度美味しい。!
 フラッシュバックコストに注意しよう!
フラッシュバックコストに注意しよう!
 フラッシュバックにも欠点はある!
フラッシュバックにも欠点はある!
 マナ・コストが高くても、直接墓地に落とせばOK!
マナ・コストが高くても、直接墓地に落とせばOK!
 墓地から取り除け!
墓地から取り除け!